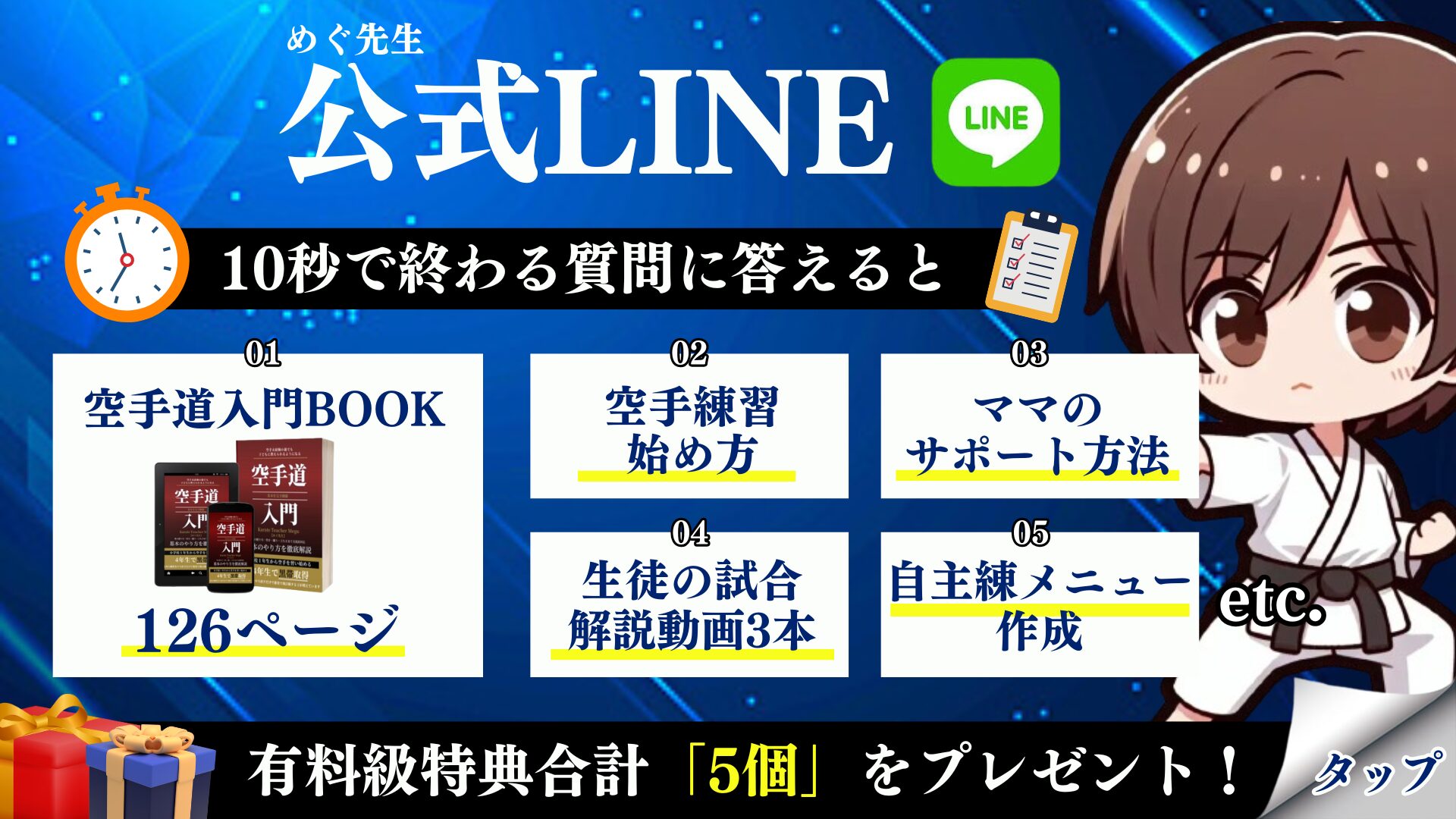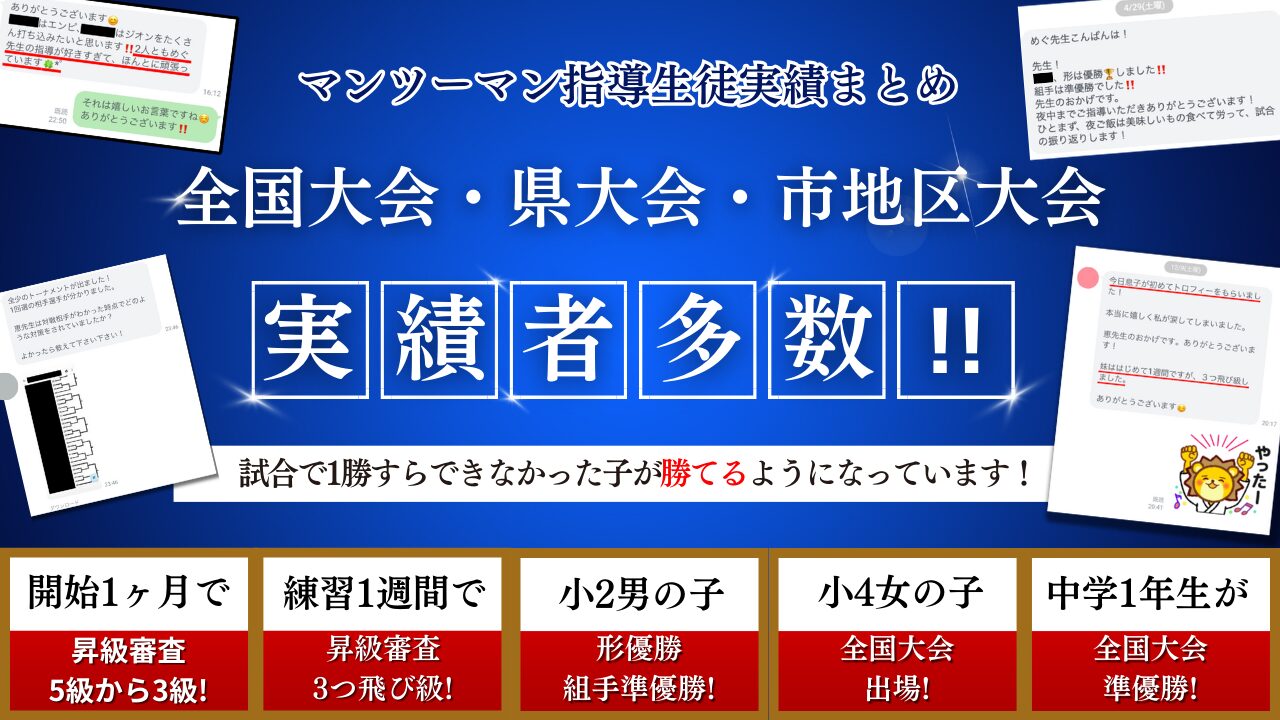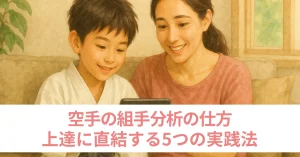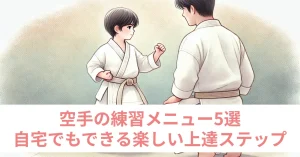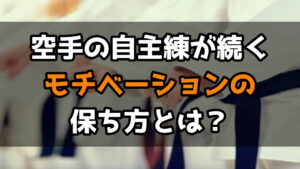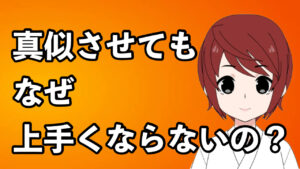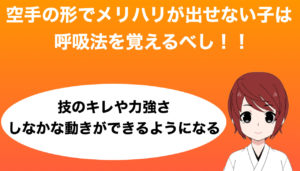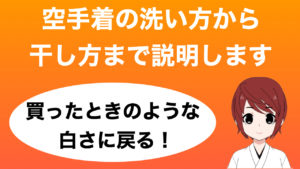「組手の試合でなかなかポイントが取れない…」
「入った!と思った技がポイントにならない」
「ポイントを取るコツを知りたいです」
組手のルールは理解していても、ポイントが入るタイミングを見極めるのは難しいと感じている方が多いですよね。
「今のポイントでしょう!」と思っても、審判の先生がなかなか旗を上げてくれないなんてよくある話です。
技を出して確実にポイントが取れるようになるためには、審判がどういう時にポイントをとってくれるのかを知っておく必要があります。

今回は、空手の組手でポイントを取る方法を初心者にもわかりやすく紹介します!
- 空手の組手でポイントを取る方法7選
- 組手のルールを活かして勝つための3つのポイント
- 初心者が陥りやすい組手のミスと4つの解決法
- 組手が上達する練習法ベスト3
- 試合で実力を発揮するための3つの準備法
子どものペースで試合を進め、確実にポイントを取れるように練習を重ねていきましょう。
空手の組手でポイントを取る方法7選
空手の組手でポイントを取るためには、手数を増やすだけではなかなかポイントが取れません。
「どの技を、いつ、どうやって使うか?」っていう戦略がめちゃくちゃ大事なんです。
今回は、組手で得点を取るために使えるテクニックを7つピックアップしてみました。
技の種類だけじゃなくて、動き方や心構えも含めて紹介していきます。
- 中段突き
- 上段蹴り
- 先手のタイミング
- 相手の動きを観察する
- フェイントを使う
- 間合い
- フォーム
特に試合で1回戦すら勝てない子は、上記のポイントを見直すことで、1回戦突破も十分に可能です。
中段突き
最初に紹介するのは、中段突き!これは組手の超定番な技です。
お腹あたりを狙うこの技は、シンプルだからこそ使いこなせたら強いんです。
「スパーン!」って気持ちよく入ったときの音がまた最高なんですよね。
でもポイントにするには、ただ当てるだけじゃダメなんです。
タイミングと気合い、それからフォームの美しさ、引手も大事な評価ポイントになります。
毎日コツコツ練習して、「これは絶対決まる!」って自信を持てるように練習していきましょう。
上段蹴り
上段蹴りって、決まったときのカッコよさがハンパじゃないんです。
得点も3点と高いので、狙えるときに出せると一発逆転を狙うこともできます。
ただし、成功させるにはバランス力と柔軟性が必要なんですよね。
最初は「足が上がらない〜!」ってなるかもしれませんが大丈夫です。
毎日ストレッチを続けてると、自然と足が上がるようになり高く蹴れるようになります。
難易度の高い技になってきますので、隠し技として練習し、試合でいつでも使えるように準備しておきましょう。
もしストレッチや効率的な練習法を取り入れたい方は、関連記事「【激変】30日で子どもの空手が上達する自主練マスター講座」にてトレーニング方法を紹介しています。試合に勝つために必要なトレーニングやストレッチを集めていますので、こちらもチェックしてみてください。
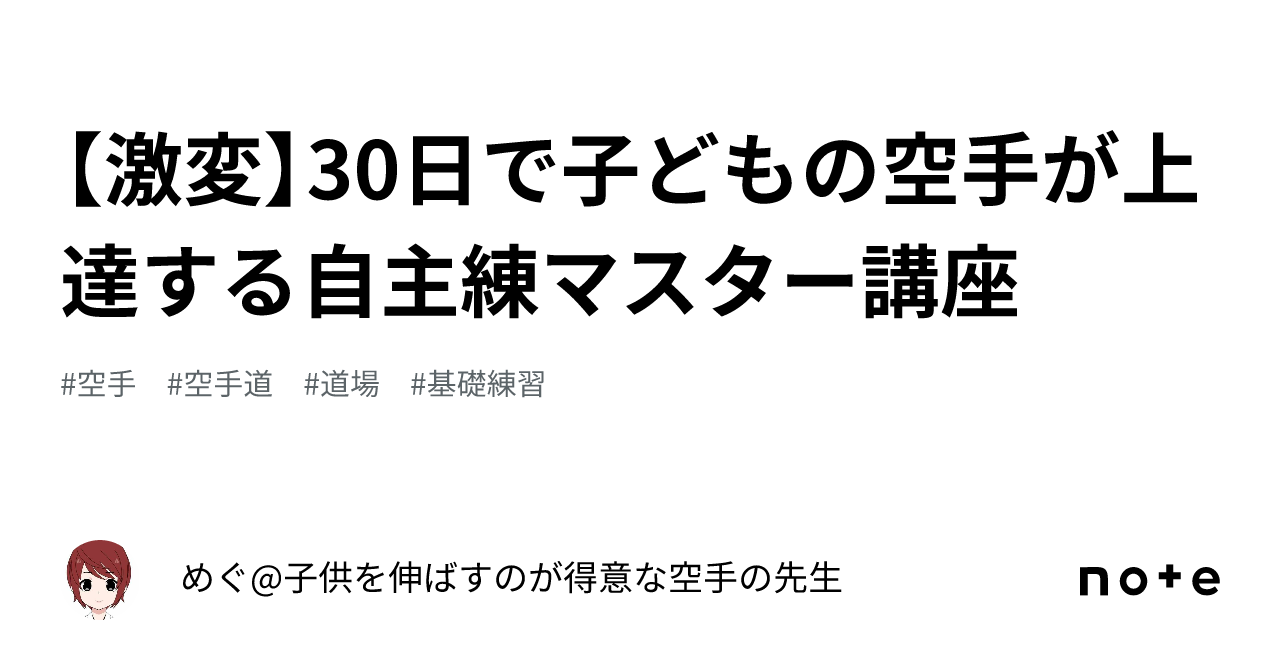
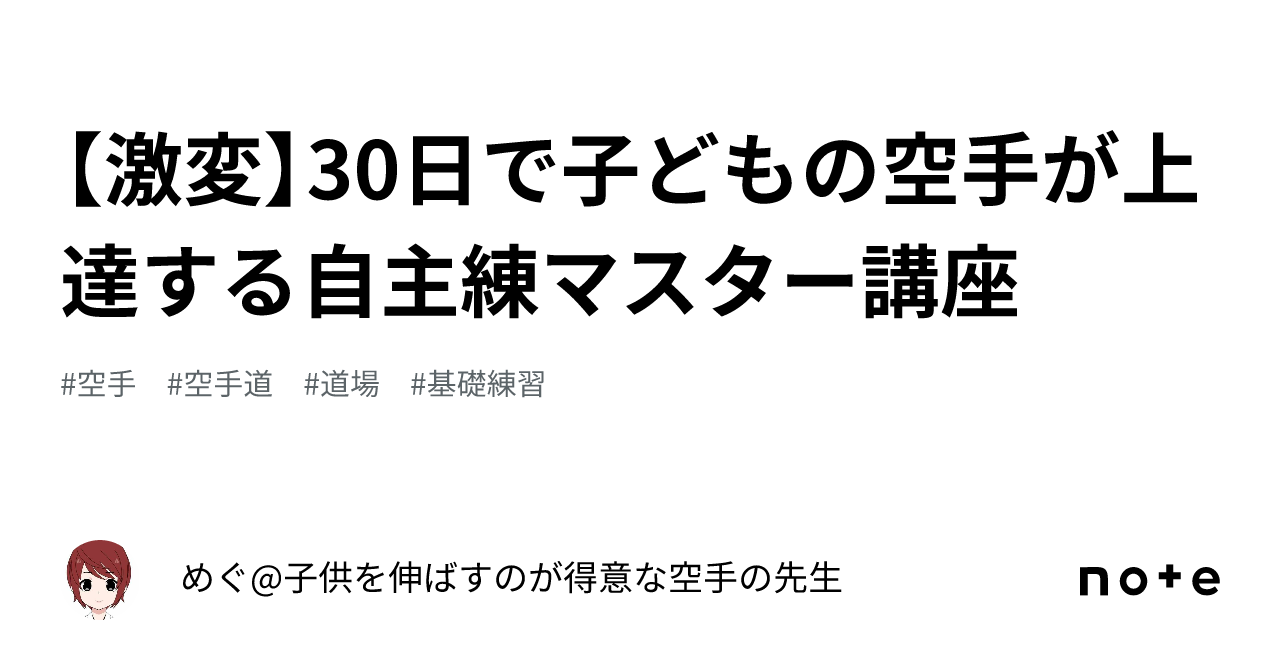
先手のタイミング
組手ってスピード勝負なところもありますので、タイミングが命だったりします。
「相手より一瞬早く!」ってだけで、技の入り方がぜんぜん違うんですよね。



ただ、焦って早く動くのとはちょっと違います。
大事なのは、「今だ!」という瞬間を見極める力です。
そのためには、相手のクセやパターンを観察することがすごく大事なので、相手の研究もしないといけないんです。
例えば、「この子、構えが低くなると突いてくるな」とか「前拳を下ろしたら蹴ってくるな」といったように、組手では相手の動きや癖を見抜くことが勝敗を分ける重要なポイントになります。
相手の動きを観察する
強い人って、相手の動きをめっちゃよく見てるんですよね。
「動きが遅い=弱い」ってわけじゃなくて、「よく観察してる=賢い」ってことなんです。
試合動画を撮っている方は、振り返っていただくとわかりやすいのですが、構え方とか、足の運び方とかを良く見てると相手のクセが見えてきます。
例えば「同じ技でポイントを取っている」とか、「中段突きで良くポイントを取られているので苦手な技なのかな」ということが分かるんです。
そういう細かいところを見抜くと、先に動いたりカウンターとることができるようになります。



組手って、実は心理戦でもあるんですよ。
観察力を味方に付ければ、戦い方がぐっと広がっていきます。
次の試合では、お子さんに前後の選手の動きをしっかり観察するように教えてあげてください。
フェイントを使う
正直言って、フェイントはめちゃくちゃ使えます。
ちょっとだけフェイント入れるだけで、相手の反応がガラッと変わることもあるんです。
例えば、上段蹴りの構えから中段突きとか、逆もまたアリです。



相手を「だます」っていうより、「読みを外させる」って感覚ですね。
しかも、決まると見てる人も「うわ!うまっ!」って思ってくれるんです。
練習のときからフェイントを入れて、相手の反応を見るクセをつけていきましょう。
フェイントがハマると、戦ってて楽しくなりますよ。
間合い
間合いって、ホントに大事なんですけど、最初はちょっと難しいかもしれません。
近すぎると技が出しづらいし、遠すぎると届かないし…ちょうどいい距離感が大切なんです。
間合いの感覚は、練習を重ねることで自然と磨かれていきますので、心配せずに続けていきましょう。
1番は自分が「技を出しやすい距離」を知っておくと、自然と動きやすくなります。
相手が近づいてきたらすっと下がる、離れたら一歩詰める…こういう練習をしていけると良いですね。
組手で一歩上を目指すなら、間合いは絶対に磨いておいて損はないです。
「間合いを制する者が、組手を制す」とも言われるように、間合いは非常に重要です。その大切さをしっかり覚えておいてください。
フォーム
最後はフォーム!技の「形」がキレイかどうかで、ポイントになるかどうか決まることも多いんです。
スピードや力だけじゃなく、姿勢や手足の伸び、軸の安定感もすごく大事。
審判に「おっ、きれいな技だな」って思ってもらえると、得点につながりやすいんですよ。
毎日ちょっとずつフォームを見直すだけでも、かなり変わります。
ビデオを撮って自分の動きを確認したり、先生にアドバイスをもらったりすることが効果的です。
フォームが改善されると、技の威力も向上するので一石二鳥です。
また、鏡を使った自主練もおすすめですので、お子さんのフォームをしっかり見直していきましょう。
組手のルールを活かして勝つための3つのポイント
空手の組手では、単に技を当てるだけではポイントにならないんです。
「ルールを理解しているかどうか」が勝敗を分ける鍵になることもあります。
どんな技が有効なのか、何が反則になるのかを正しく知っておけば、余計な減点を防げます。
また、ルールを逆手に取った戦略も立てられるようになります。
- 有効打突
- ポイント配分
- 反則対策
試合での駆け引きを制するために、まずは基本を押さえておきましょうね。
有効打突
組手では「有効打突」と認められた技だけがポイントになります。
つまり、軽く触れただけではだめなんです。
技が決まっていても、姿勢や気合い、引手がないと、ポイントが認められないこともあります。
体の中心に向かってしっかり打ち込むこと、そして「気合い」をしっかりと出しながら技を出すことが大切です。この2つを意識することで、技に力強さと精度が増します。
気持ちが乗っているかどうかは、審判にも伝わってしまいます。
だからこそ、一本一本の技で確実にポイントを取るつもりで攻めていくことが大切なんですよね。
なんとなく出した技ではポイントにならないことの方が多いので、技を出すのがもったいないです。技を出すのであれば、しっかりと狙って技を出すように心掛けていきましょう。
ポイント配分
空手の組手では、技ごとに得られる点数が違います。
上段突きや中段突きやワンツーなら1点、中段蹴りは2点、上段蹴りや裏回し蹴りなら3点になります。
つまり、どんな技で攻めるかによって、逆転勝ちも狙えるんです。
例えば、残り時間が少ないときに一発で3点を狙う作戦なんかもアリです。
常に自分と相手の得点を把握して、冷静に戦略を変えていくのがコツです。
特に負けてしまうと焦ってしまい、高得点な技ばかり狙って外してしまう子もいます。
だからこそ、負けているときにどのように仕掛けていくかを事前に作戦として練っておくことも大切です。
焦らず、冷静に戦うための心構えが勝利への鍵となります。
反則対策
どんなに技がうまくても、反則を取られてしまっては本当にもったいないですよね。
組手の反則には、過剰な接触・時間稼ぎ・場外・顔面への過剰な攻撃など、細かいルールがたくさんあります。
特に初心者のうちは、熱くなってつい手が出すぎてしまうこともよくあります。
だからこそ、落ち着いて冷静に動くことが大切です。練習の段階から「これって反則にならないかな?」と意識して動きを確認するクセをつけておくと安心です。
また、審判の立場に立って考えることで、ルールへの理解も深まりますし、相手の反則にも気づけるようになります。
ルールを味方にすることも、勝つための大事な力なんです。
初心者が陥りやすい組手のミスと4つの解決法
組手の練習を始めたばかりのころって、うまくいかないことだらけですよね。
でも、それってみんなが通る道なんです。
よくあるミスにはパターンがありますので、それを知っていれば対策できます。
失敗を怖がるより、「気づけてラッキー!」って思えると成長が早くなりますよ!
今回は、初心者が陥りやすい組手のミスと、すぐに実践できる解決法を紹介します。
- 攻め急ぎ
- ガードのミス
- 見せ方の工夫
- 引手を引かない
お子さんもやってしまっていないか、確認してみてください。
攻め急ぎ
お子さんって試合になると、つい焦って先に技を出したくなることありませんか?
ただ、焦って動くとフォームや構えが乱れて、体に隙ができやすくなり、逆にカウンターを受けるリスクが高まります。
大切なのは、相手のペースにのまれることなく「お子さんのタイミングで動くこと」なんです。
練習では「一拍おいてから動く」ことを意識させてみてください。
それだけで、相手の動きがよく見えて、判断力もグッと上がってきます。
焦らず、自分の“間”で動けるようになると、自然と自分のペースで試合運びができるようになります。
相手のリズムにのまれず、お子さんのペースで戦えるように練習していきましょう。
ガードのミス
防御が甘くなると、簡単にポイントを取られてしまいます。
特に攻撃に集中しているときほど、ガードが下がりがちなんですよね。
ミット練習や対人で、技を出したあとにすぐ構えを戻す練習をしておくと良いでしょう。
「守りながら攻める」という意識が身につくと、組手の質が一気に上がります。
また、正しい構えができていれば、無駄な動きが減ってスタミナも温存できます。
自分の身体を守るためにも、ガードはとっても大事なんですよね。
「攻撃は最大の防御」じゃなくて、「防御があってこその攻撃」なんです。ぜひ覚えておいてください。
見せ方の工夫
組手では、技の「見せ方」もすごく大事なんです。
ただ当たっただけでは、審判に伝わらないことも多いんですよね。
大きな声を出す、技を出した瞬間にピタッと止まるなど、印象を強く残す動きが必要です。
そうすると、審判にも技が「入った!」ってアピールできます。
鏡の前での練習や、動画撮影してお子さんの動きを確認するのもおすすめです。
「見せる組手」を意識すれば、旗が上がりやすくなることもあります。
試合って舞台みたいなものなので、見ている人に「伝わる動き」を意識することも大切なんですよ。
引手を引かない
意外と見落とされがちなのが、「引手(ひきて)」です。
技を出したあと、しっかりと手を脇腹まで引かないと、ポイントとして認められないこともあります。
組手ではスピード重視になりがちなので、引手が雑になってしまうことが多いんです。
でも、引手がしっかり引けてると、技のキレが増して威力も伝わりやすくなります。
審判からの見た目もよくなるので、ポイントが入りやすくなります。
普段のミット打ちから「引手を忘れずに!」って意識するだけで、改善できます。
細かいところですが、勝負を左右する大きな要素なんで、しっかり引手を意識させましょう。
組手が上達する練習法ベスト3
「もっと強くなりたい!」「試合で勝ちたい!」そんなときに大切なのが日々の練習です。
でも、やみくもに練習するだけでは、試合で勝てるようにはなりません。
だからこそ、上達しやすい練習法を選んで効率的にステップアップする必要があります。
今回は、組手が上達する「自宅でもできる練習法ベスト3」を紹介します。
- ミット打ちの練習
- 間合いの練習
- 反応速度を鍛える練習
どれも今日からできる内容ばかりなので、ぜひお子さんと一緒にチャレンジしてみてください。
ミット打ちの練習
まずは定番中の定番、ミット打ちの練習です。
突きや蹴りを思いっきり打ち込めるから、爽快感もバツグンなんです。
フォームを確認しながら何度も繰り返せば、技の正確さとスピードがどんどんアップします。
「パーン!」と気持ちいい音が鳴ると、「おっ、今のよかった!」ってすぐにわかるようになります。
またお子さんの動きを動画に撮って見返すと、新たな気づきもありますよ。
特に蹴り技は、ミットで練習すると安定感が増すのでおすすめです。
相手がいなくても1人でできるので、自主練でやってみてください。
間合いの練習
間合いの練習は、組手において非常に重要です。相手との距離感を正確に掴むことで、攻撃を避けたり、反撃するタイミングを見極められるようになります。
練習方法は、相手と適切な距離を取りながら、お互いに攻撃と防御を繰り返すことです。
まず、相手の動きに応じて自分がどの距離にいると相手の技を貰わないのかを確認します。
次に、相手が攻撃してきた際に、どのタイミングで避けて反撃ができるかを意識して練習します。
この反復練習を通じて、試合の中で「間合い」を自然に感じ取れるようになるはずです。
距離を上手く取ることで、攻撃を避けるだけでなく、自分から攻めることもできるようになります。
まずは、間合いのコツを掴めるように練習していきましょう。
反応速度を鍛える練習
組手では素早い反応が求められます。攻撃を受けた瞬間、どう反応するかが試合の結果を大きく左右します。
練習方法は、相手の攻撃に対して素早く受けたり払ったりしながら反撃できるよう反応を鍛えることです。
例えば、パートナーに軽く技を当ててもらい、その後素早く防御や反撃をする練習を行います。
反応速度を意識的に高めることで、よりスムーズに技を出すことができます。
これにより試合中に落ち着いて対応し、勝負を有利に進められるようになります。
練習を繰り返すことで、組手のスキルが向上します。
結果として、試合でも安定して強さを発揮できるようになるでしょう。
試合で実力を発揮するための3つの準備法
試合当日、「緊張しちゃって思うように動けていないなぁ…」ってお子さんの試合を見ていて思うことはありませんか?
実は、試合で実力を発揮するためには「準備の仕方」が超重要なんです。
練習の成果をしっかり出すためにも、心と体のコンディションを整えておきたいですよね。
ここでは、当日に向けてやっておくと安心な3つの準備法をご紹介します。
- ルーティン
- メンタル
- 審判の位置
道場の先生や他の先生もここまで細かく教えてくれる先生は少ないと思いますので、お子さんが本番で「いつも通り」の自分を出せるようになるコツをしっかり押さえておきましょう。
とくに3つ目はあまり表では教えたくない内容なので、有益な情報です。ぜひ参考にしてみてください。
ルーティン
スポーツ選手がよくやってる「ルーティン」、実はすごく効果的なんです。
例えば「コートに立ったら深呼吸を2回」「試合前にジャンプを3回」とか。
毎回同じ動きをすることで、心を落ち着ける効果があります。
日頃から練習に取り入れておくことで、試合でも自然に動けて安心できます。
「これをやれば落ち着く」って自分なりの方法があると、自信につながります。
大切なのは「リズム」と「いつも通り」って感覚です。
お子さんと一緒に、お子さんだけのルーティン、探してみてください。
メンタル
いくら技術があっても、メンタルが不安定だと本来の力は発揮できません。
せっかく頑張ってきたのに、緊張で動けなくなるのはもったいないですよね。
大事なのは、「失敗してもいいや」って思える余裕を持つことです。
「勝ちたい」よりも「楽しみたい!」って気持ちで試合に臨むと、意外と力を出せますよ。



「勝たなきゃ」と思いすぎていた頃の私は、緊張で動きが硬くなり、力を出し切れない試合もありました。でも「楽しめればOK」と思って臨んだ試合のほうが、動きが良かったんです。自分にプレッシャーをかけすぎないこと、それも勝つための大事なコツですね。
例えば、深呼吸したり、好きな音楽を聞いたり、自分の気持ちが落ち着く方法を見つけておくとよいでしょう。
あと、試合前日はちゃんと寝て、朝ごはんをしっかり食べるのも超重要です。
心と体、どっちも整っていれば、本番もバッチリですよ!
審判の位置
これ、あまり教えている先生も少ないんですが…「審判の位置」、実はかなり重要なんです。
どんなに良い技を出しても、審判の死角に入っていたら「見えない=ノーポイント」になってしまうんですよね。
だからこそ、技を出すときは審判の正面か、よく見える角度を意識して技を出させるようにしてみてください。



相手の陰にならないように動くのもコツです!
少し角度を変えて技を出すだけでも、ポイントを取りやすくなります。
形(型)に見せ方があるように、組手も「技が入った!」と審判に伝わるアピールが大切です。
技の確かさだけじゃなく、見せ方も勝負の一部なんです。
自信がない子でも、引手をしっかり引くだけで技が際立ってアピールになります。
だからこそ、普段の練習から“魅せる動き”を意識しながらお子さんと一緒に練習していきましょう。
まとめ
今回は「【初心者必見】空手の組手でポイントを取る方法7選|技・タイミング・ルールのコツを解説」というテーマでお話しをしましたが、いかがでしたか?
組手でポイントを取るには、技術だけでなくタイミングや気持ちの準備も大切だということ、少しでも伝わっていたら嬉しいです。
最初はうまくいかなくても、「今の、なんかいい感じだったかも!」という手ごたえを感じる瞬間が、きっと訪れます。
お子さんのひたむきな努力が、次の1点につながりますように…。
ぜひ、試合や練習の前にまたこのページを読み返して、気持ちを整えるきっかけにしてくださいね。応援しています!