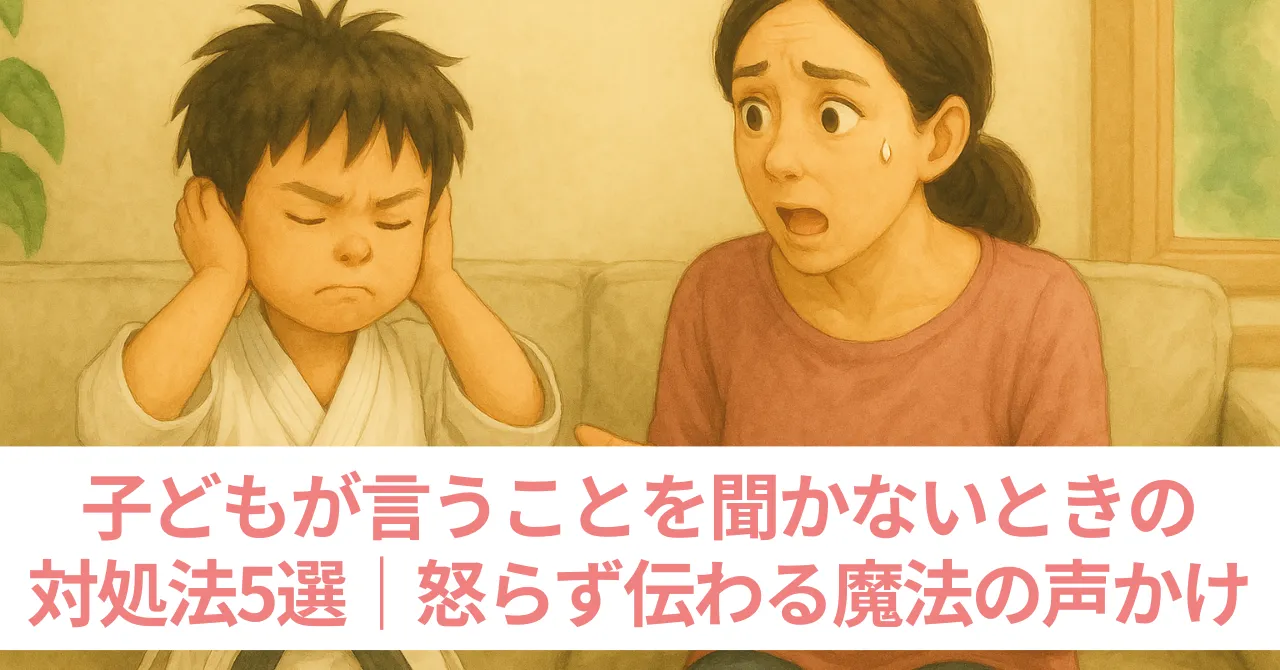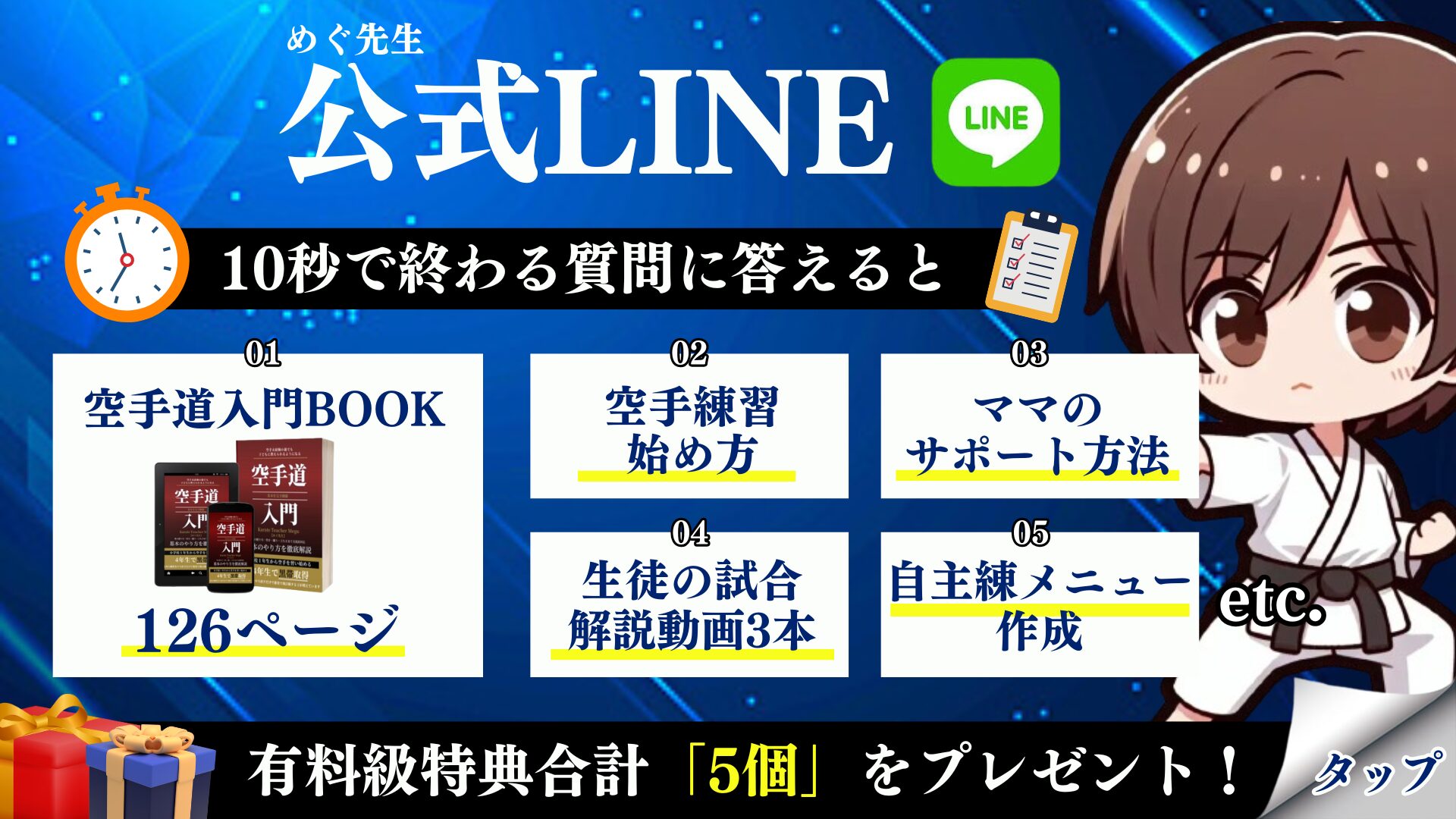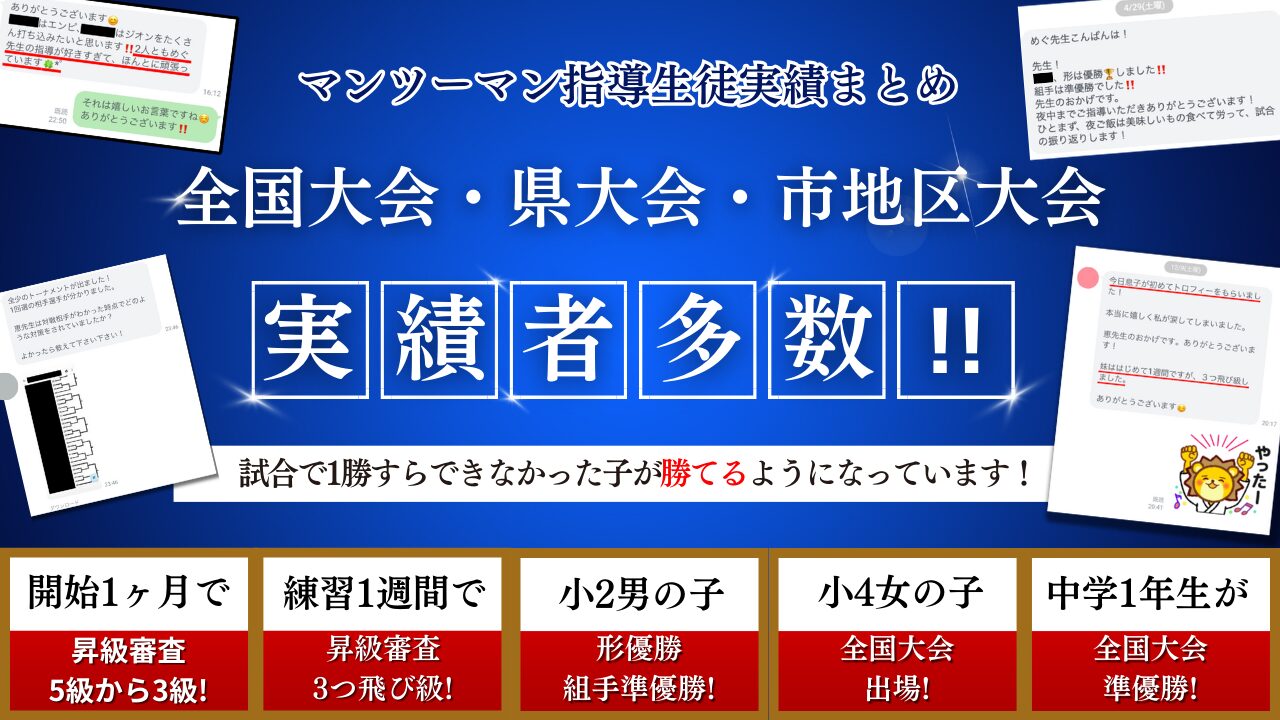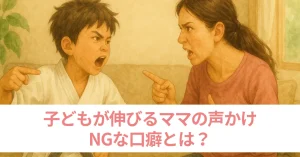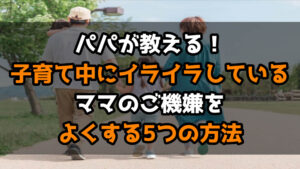「子どもが全然言うことを聞いてくれない…」
「何度も同じことを言っているとストレスが溜まってしまう」
「子どもに伝えたいことがうまく伝わらず、イライラしてしまう」
子どもに何度も同じことを言っても、なかなか言うことを聞いてくれないと、どうしたらいいのか分からなくなってしまうこと、ありますよね。
でも実は、“言うことを聞かない”のは成長の証だったりするんです。
この記事では、子どもが言うことを聞かない理由と、その対処法をやさしく分かりやすく紹介していきます。
この記事を読むことで、親としての言葉の選び方や、子どもにうまく伝える方法を学べるでしょう。ぜひご覧ください!
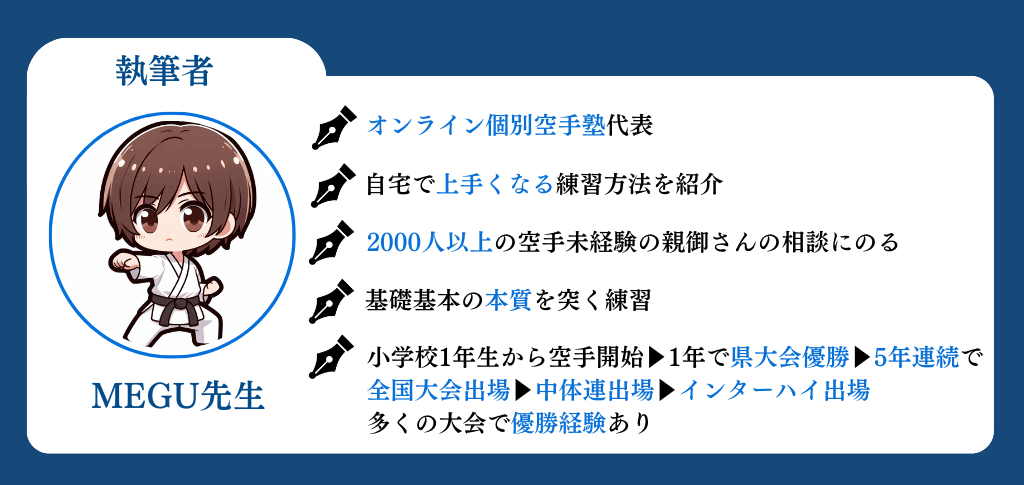
子どもがいうこと聞かないときの対応法5選
子どもが言うことを聞かないとき、親としては困ってしまいますよね。
でも、実はその裏には子どもなりの理由や気持ちが隠れていることが多いんです。
この章では、すぐに実践できる効果的な5つの対応法をご紹介します。
- 共感から始める
- 選択肢を与える
- 環境を整える
- 親の感情整理
- 一貫性を持つ
「怒らずに、でも伝えなければならないことはきちんと伝える」ためのコツをお教えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
共感から始める
子どもが反発しているとき、まずは「そう思っていたんだね」と気持ちを受け止めてあげることが大事です。
例えば「イヤ!」と叫んでいても、実は不安だったり、眠かったりするんですよね。
こちらが感情的になる前に、「どうしたの?」って落ち着いて聞いてあげるだけで、驚くほど空気が変わります。
共感の言葉って、子どもにとって安心できる“魔法の鍵”みたいなものです。
頭ごなしに叱るよりも、まず寄り添うことで、子どもは自分の気持ちに整理がつくようになります。
そのうえで次のステップに進めば、親の話もしっかり届くようになりますよ。
はじめは時間がかかるかもしれませんが、信頼関係が少しずつ育まれていきます。
選択肢を与える
子どもに選択肢を渡すと、「自分で決められる」って気持ちになれるんですよね。
「今お風呂に入る?それとも5分後にする?」みたいに聞くだけで、かなり反応が変わることもあります。
命令されると「やだ!」ってなるのに、自分で選ぶと動きやすくなるって不思議ですよね。
これって、子どもが“自分の意志で動いた”って実感できるからなんです。
もちろん、選ばせるのは「どっちでもいい」範囲でOKです。
親の希望から大きく外れない選択肢を2つくらい提示するのがコツです。
小さなことでも選ぶ練習になるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。
環境を整える
実は子どもが言うことを聞かない理由って、環境のせいだったりもするんですよ。
例えばテレビがついていたり、スマホが目の前にあったりすると、そっちに集中してしまいますよね。
「何回言っても聞かないな〜」ってときは、一度まわりを見渡してみてください。
話しかけるときに、おもちゃを片付けるとか、静かな場所に移動するとか。
まずは「子どもが受け入れられる状態かどうか」を確認することが大切なんです。
親の感情整理
「言うこと聞かない!」ってなると、親もついイライラしてしまいますよね。
でもそのイライラ、子どもはちゃんと感じ取っているんです。
親が怒ってると、子どもはますます反発するし、話をシャットアウトしてしまいます。
だからこそ、まずは親自身が少し落ち着くことが大事なんですよね。
深呼吸したり、「いま私は疲れてるなぁ」って自分の気持ちに気づいてあげること。
そのあとで、ゆっくり話しかけてみてください。
感情をコントロールするのって難しいですが、親の気持ちが安定してると、子どもも安心します。

子育てって、まず“自分を整える”ところからだったりするんですよね。
一貫性を持つ
子どもって、親のルールが毎回変わると「これって本当に守らなきゃダメ?」って思ってしまうんです。
例えば、昨日はOKだったのに今日はダメって言われたら、大人でも混乱しますよね。
だからこそ「これは絶対」「これはOK」といった基準をブレずに持つことが大切なんです。
とくに叱るときや注意するとき、一貫した対応が子どもにとっての安心につながります。
もちろん、柔軟さも必要ですが、「これだけは変わらない」という芯があると、子どもは理解しやすいんですよ。
家庭のルールを簡単に書き出して、見える場所に貼っておくのもいいかもしれませんね。
一貫性があると、子どもも「これがうちのやり方なんだ」と納得してくれるようになります。
親がやってはいけないNG対応5つ
子どもにイライラしたとき、つい取ってしまう行動ってありますよね。
でも実は、その行動が逆効果だったり、子どもの反発を生む原因になっているかもしれません。
ここでは、子どもにNGとされる親の対応を5つ紹介します。
- 怒鳴る・感情的に叱る
- 脅す・強制する
- 無視する・放置する
- 罰を与えるだけ
- 子どもの人格を否定する言葉
「そんなつもりじゃなかったのに…」と思い当たることもあるかもしれません。順番に見ていきましょう。
怒鳴る・感情的に叱る
「ついカッとなって怒鳴っちゃった…」そんな経験、誰にでもありますよね。
でも、感情で怒鳴られると、子どもは「怖い」という気持ちばかりが残ってしまいます。
そうすると、「何がいけなかったのか」が伝わらなくなってしまうんです。
叱るときは冷静に、伝えたいことをはっきり言うほうが、実は効果的なんですよ。
怒鳴る代わりに、「今はこうしてほしかったな」とトーンを落として伝えてみてください。
感情的な怒りは、子どもとの信頼関係を壊しやすくなってしまいます。
親も人間だからイラッとするのは当たり前。でも、気持ちを落ち着けて話す努力をしてみましょう。



「伝える」と「怒鳴る」は、まったく別のアプローチなんです。
脅す・強制する
「言うこと聞かないと置いていくよ!」「おもちゃ捨てるよ!」と言ったことありませんか?
こういう言葉は、一時的には効くかもしれませんが、長期的には信頼関係を傷つけてしまうんです。
子どもは「また脅される」と思ってしまい、親の言葉を素直に受け取れなくなります。
それに、子ども自身が“怖さ”で動くようになってしまうのも心配ですよね。
その代わりに、「どうすればお出かけできるかな?」と一緒に考えるようにしてみましょう。
強制や脅しより、納得感のある対応の方が子どもは自分から動こうとします。
信頼は一朝一夕では築けませんが、小さなやりとりの積み重ねで変わってきます。
「怖がらせて動かす」のではなく、「分かり合って進む」方へシフトしてみましょう。
その方が、親も子もずっとラクになれますよ。
無視する・放置する
子どもが癇癪を起こしたとき、「もう知らない!」って無視しちゃいたくなること、ありますよね。
でも、無視されたと感じた子どもは「自分は大切にされていない」と感じてしまうことがあります。
もちろん、冷却時間が必要なときもありますが、それと“放置”は違います。
ちゃんと「落ち着いたらお話しようね」って声をかけてあげるのが大切です。
それだけで、子どもは少しずつ安心して感情を整えられるようになります。
小さな声がけが、子どもの心に届くんですよ。
罰を与えるだけ
「言うこと聞かないならおやつなし!」って、つい言ってしまったことありませんか?
たしかに一時的には効くかもしれませんが、それが繰り返されると、子どもは罰を避ける行動しか考えなくなってしまいます。
「怒られないように」「バレないように」って、言い訳がうまくなるだけで、本質は変わらないんです。
ダメなことは伝えつつ、「なぜ?」と「どうしたらいいか?」を一緒に考える姿勢がポイントです。
罰よりも、学びやすい空気をつくっていきたいですね。
子どもの人格を否定する言葉
「なんでこんなこともできないの?」「バカだね」など、つい口から出てしまうこともありますよね。
でもこの言葉、実はとっても危険なんです。
一度でも言われたことって、子どもの心に深く残ってしまうんですよ。
「自分はダメな子なんだ…」って思わせてしまうと、自己肯定感がガクンと下がってしまいます。
大切なのは、行動を注意することであって、「あなたそのもの」を否定しないこと。
例えば「片付けない子ね!」じゃなくて、「片付けがまだ終わってないよ〜」という言い方にするだけで、印象はかなり違います。
子どもは大人の言葉をそのまま信じて、自分の価値を決めてしまいがちなんですよね。
だからこそ、注意するときこそ、優しい言葉選びを意識したいですね。
年齢別!言うことを聞かない理由と対策
子どもが言うことを聞かない理由って、年齢によって全然ちがうんです。
2歳のイヤイヤと、小学生の反抗は、まったく別物なんですよね。
この章では、年齢ごとに「どうして聞かないのか?」という理由と、それに合った対応法を紹介していきます。
- 2~3歳の「イヤイヤ期」
- 4~6歳の「自立心の芽生え」
- 小学生の「反抗の始まり」
- 思春期の「自我の確立」
子どもの成長に合わせた対応を知ることで、ムダなストレスも減らせるでしょう。
2~3歳の「イヤイヤ期」
「なんでもイヤ!」って言われる時期、まさにイヤイヤ期ですね。
この時期は、自分の気持ちを主張する練習をしているんです。
「自分でやりたい!」って気持ちと、「でもまだうまくできない」ってジレンマで、子どもは大混乱なんですよ。
その結果、全部に「イヤ!」って言ってしまうんです。
ここで無理やり言うことを聞かせようとすると、逆にぐずりが激しくなってしまいます。
対応のコツは、「選択肢を与えること」と「気持ちの共感」です。
イヤイヤ期は子どもが自分の感情や意見を表現し始める成長の過程です。焦らず、優しく見守りながら支えてあげることが大切です。
4~6歳の「自立心の芽生え」
この時期になると、子どもは「自分で考えて行動したい!」という気持ちが強くなります。
でも、まだ社会的なルールや周囲の空気を読む力は育ちきっていないんですよね。
だから、「ダメって言ってるのに、なんでやるの?」って行動が目立つんです。
この頃の反発は、言うことを聞かないというより、“自分の考え”を出そうとしている証拠なんですよ。
親としては、まず「自分で考えてるんだね」と認めてあげることが大切です。
そのうえで、「ここまではOK」「ここからはダメ」とルールをしっかり伝えていきましょう。
子どもが自分で判断できる場面を少しずつ増やしていくと、自立心がどんどん育っていきます。
正解を押しつけるより、子ども自身の「やってみたい」を応援する気持ちがポイントです。
ルールの中で自由に動ける環境をつくってあげましょうね。
小学生の「反抗の始まり」
小学生になると、少しずつ「親の言うことがすべて正しいとは限らない」と気づき始めます。
ここがいわゆる“軽い反抗期”の入り口なんですよ。
でも、それは成長の一環であって、決して悪いことではありません。
自分の考えを持ち始めた証拠なので、むしろ前向きな変化なんです。
対応のコツは、「正論でねじ伏せない」こと。
大人としては言い負かしたくなるけど、それをすると子どもは心を閉ざしてしまいます。
「そう思うんだね。でもママはこう考えてるよ」と、対等な会話を心がけてみてください。
意見を聞いてもらえる経験は、子どもの自己肯定感を育ててくれます。
“反抗”じゃなくて“自己表現”として受け止めてみましょう。
思春期の「自我の確立」
思春期はまさに「自分って何?」を探す時期。
親の言うことより、友だちや社会の中での自分を大事にし始めるんですよね。
「うるさいな」「関係ないでしょ」って返されると、つらく感じるかもしれません。
でも、これは「自分で考えたい」っていう気持ちの表れなんです。
この時期の対応は、“信頼して見守る”ことがポイントです。
何か言いたくても、まずは「信じてるよ」と伝えることが大切です。
必要なときに手を差し伸べられるよう、距離感を保ちつつサポートしましょう。
子どもに響く伝え方のコツ5つ
同じことを言っても、伝え方ひとつで子どもの反応ってガラッと変わるんですよね。
例えば「早くしなさい!」と「そろそろ出発しようか」では、受け取り方がまるで違います。
この章では、子どもにちゃんと届く伝え方のコツを5つご紹介します。
- 短く具体的に伝える
- 肯定的な声かけをする
- 目線を合わせて話す
- タイミングを見て話す
- 感情ではなく行動を伝える
「なんで聞いてくれないのかな…」と悩んでいたら、まずは“伝え方”を見直してみましょう。
短く具体的に伝える
子どもに伝えるときは、なるべく「短く・具体的」にするのが鉄則です。
「ちゃんとしなさい」じゃなくて、「靴をそろえてね」「イスに座ってね」のようにハッキリ言うことが大事なんです。
抽象的な言葉って、大人でも迷っちゃうときありますよね。
子どもならなおさら、「なにをどうすればいいの?」って混乱してしまいます。
「もうすぐごはんだよ」より「あと5分で食べるよ」とか、数字を入れるのも効果的ですよ。
具体的に伝えれば、子どもは「自分にできそう!」って感じて動きやすくなります。
長々と説明するより、シンプルな言葉の方がちゃんと届くんですよね。
わかりやすさって、親子のコミュニケーションの基本かもしれません。
言いたいことはギュッとひとことにまとめてみてくださいね。
肯定的な声かけをする
「〇〇しないで!」ってつい言ってしまうこと、ありませんか?
でも、否定的な言葉って、子どもには意外と伝わりにくいんです。
例えば「走らないで!」よりも、「歩こうね」の方が子どもはイメージしやすいんですよ。
否定されると、「ダメなのはわかるけど、じゃあどうしたらいいの?」って感じてしまうことがあります。
だからこそ、「してほしいこと」をポジティブに伝えると、子どもは安心して行動しやすくなります。
目線を合わせて話す
子どもに話すとき、立ったまま声をかけていませんか?
目線を合わせてしゃがんで話すだけで、ぐんと伝わりやすくなるんですよ。
それは、子どもが「ちゃんと向き合ってもらえてる」と感じられるからなんです。
上から言われると、どうしても「怒られてる…」って思ってしまうんですよね。
でも、目を見て話せば、気持ちもまっすぐ届きやすいんです。
とくに小さい子は、表情や声のトーンで安心感を得ることが多いんです。
だからこそ、姿勢や顔つきもコミュニケーションの一部なんですよ。
毎回じゃなくてもいいので、意識して目線を合わせる習慣をつけてみましょう。
タイミングを見て話す
子どもがテレビに夢中になっているときに「練習しなさい!」と言っても、なかなか耳に入らないものです。
子どもにも、集中しているときや疲れているときがあるので、そんなタイミングで声をかけても逆効果になることが多いんです。
少し落ち着いているときや、アイコンタクトが取れたときに話すと、自然と伝わります。
「今なら伝わるかも」という空気を読む力は、親にも大切なスキルです。
例えば、おやつの後や遊びが終わった後などが絶好のタイミングです。
話すタイミングを工夫するだけで、同じ言葉でも全く違った意味を持つことになります。
“言う内容”だけでなく、“言うタイミング”が本当に重要なんですね。
焦らずに、落ち着いたタイミングを見計らって話しかけてみましょう。
感情ではなく行動を伝える
子どもが言うことを聞かないと「もうイヤ!」「イライラする!」って気持ち、わかります。
でもそのままぶつけると、子どもには「怒ってる」しか伝わらないんです。
大事なのは、どうしてその感情になったのかを“行動”で伝えること。
例えば、「ママはイライラしてるの。なぜなら靴が散らかっていたから」って言えば、理由が伝わりますよね。
子どもは、「どうすればよかったのか」がわからないと、次にどう行動すればいいか学べないんです。
だから、「〇〇ができてないよ」「次はこうしてほしいな」と行動ベースで伝えていくのがポイントです。
感情をぶつけるのではなく、冷静に“事実”として伝えることで、子どもも理解しやすくなります。
親の心がラクになる考え方
子どもが言うことを聞かないと、つい「私の育て方が悪いのかな…」と心配になることがありますよね。
でも、実は子育てに「正解」なんてないんです。
がんばっているのにうまくいかない日もあって当然。
この章では、親の心がちょっとラクになる「考え方のヒント」をお伝えします。
- 完璧じゃなくていい
- 「聞かない」のは成長の証
- 他の子と比べない
- 一人で抱え込まない
- できたことを認め合う
子育ては、がんばりすぎなくていいんです。「ちゃんとしなきゃ」を少し手放すだけで、子どもとの毎日がもっとやわらかく、心地よくなっていきますよ。
完璧じゃなくていい
「もっとちゃんとしなきゃ」
「もっとしっかり育てなきゃ」
そんなふうに、自分にプレッシャーをかけてしまうこと、ありませんか?
でも、大丈夫。完璧な親なんて、どこにもいません。
むしろ、ちょっとドジだったり、抜けているところがある親のほうが、子どもは安心できるんです。
がんばりすぎて、笑えなくなってしまったら…それは子どもにとっても、少しさみしいことかもしれません。
失敗してもいい。間違えても、やり直せばいい、そんな姿を見せることこそ、子どもにとっての大きな学びになります。
「自分のままでいいんだ」って、子どもが感じられるように、まずは親が、自分にやさしくしてあげてください。
ときには、深呼吸して「ま、いっか」と笑える気持ちを忘れずに。
親だって人間です。がんばりすぎず、のびのびと子どもと向き合っていきましょう。
「聞かない」のは成長の証
子どもに対して「どうして言うこと聞かないの?」って思うこと、ありますよね。
でも、それって“自分の意思を持てるようになってきた”ってことでもあるんです。
赤ちゃんのときは、親の言う通りに動いてましたよね。
だけど、成長すると「イヤだ」「違う」と主張するようになります。
それこそが“心が育ってるサイン”なんですよ。
実は「言うことを聞かない=ダメなこと」ではないんです。
ぶつかり合いの中で、子どもも学んでいきます。
「うちの子、ちゃんと成長してるな」って前向きに受け止めてみてください。
他の子と比べない
「あの子はあんなにしっかりしてるのに、うちの子は…」と思ってしまうことありませんか。
でも子どもは、それぞれに違う“育ち方”をしています。
早くできるようになる子もいれば、時間をかけて少しずつ成長する子もいます。
比べれば比べるほど、親も子どももどんどん苦しくなってしまいます。
大切なのは、その子のペースで一歩ずつ成長していること。
「まだできないこと」じゃなくて、「今日はこれができた!」に目を向けてみましょう。
昨日より笑顔が多かった。親が何も言わずに練習していた。それだけでも立派な前進です。
子育ては他の子と比べることではなく、昨日の自分と比べてどれだけ成長したかが大切です。
一人で抱え込まない
「私がちゃんとしなきゃ」と、すべてを抱え込んでいませんか?
でも、子育ては一人でやるものではありません。
パートナーや家族、友だち、専門家…いろんな人にもっと頼っていいんです。
無理してがんばりすぎると、笑顔もなくなってしまいます。
「ちょっと話を聞いてほしい」「今日は大変だった」と、誰かに気持ちを伝えるだけで心が軽くなります。
同じように悩んでいる親はたくさんいます。ひとりじゃないと思うだけで、気持ちが楽になりますよ。
辛くなる前に、SOSを出してみてくださいね。助けを求めることは、弱さじゃなくて“強さ”なのです。
できたことを認め合う
子育てって、どうしても「できていないこと」に目が行きやすいですよね。
でも、できたことにもちゃんと注目してあげてください。
例えば、朝しっかり起きられた、忘れ物をしなかった、時間を守って行動できたなど、これもすべて立派な成長です。
「今日も素晴らしかったね」「ママも頑張ったよ」とお互いに言えると嬉しいですよね。
親も子も、お互いを認めることで、自信が育っていきます。
完璧じゃなくても、お互いを褒め合える関係って、素晴らしいと思いませんか?
「できていないこと」ではなく、「できたね!」と声をかけ合うことで、毎日がもっと温かく、優しいものになりますよ。



毎日ひとつ、子どもの良いところを見つけてみましょう。
まとめ
子どもが言うことを聞かないとき、本当に大変ですよね。
でも、怒る前に少しだけ立ち止まって、「この子は何を伝えたいのかな?」と考えてみると、違った視点が見えてくることがあります。
大切なのは、子どもの“気持ち”に寄り添い、伝え方を少し工夫すること。
完璧な対応なんて必要なくて、「伝えようとする気持ち」が大事なんです。
あなたは今も立派に子育てをしていて、とても素晴らしい親です。毎日の子育て、本当にお疲れ様です。