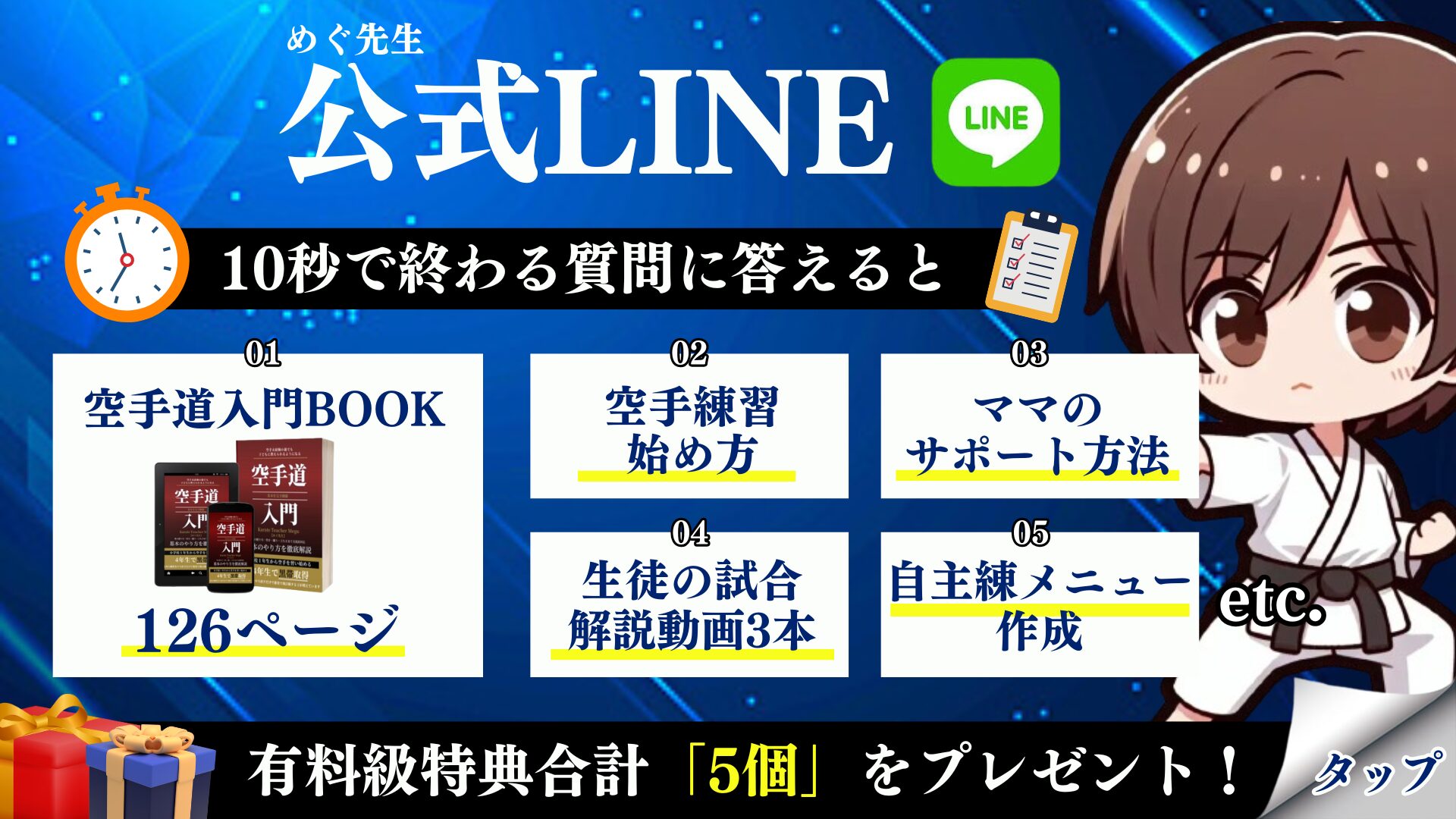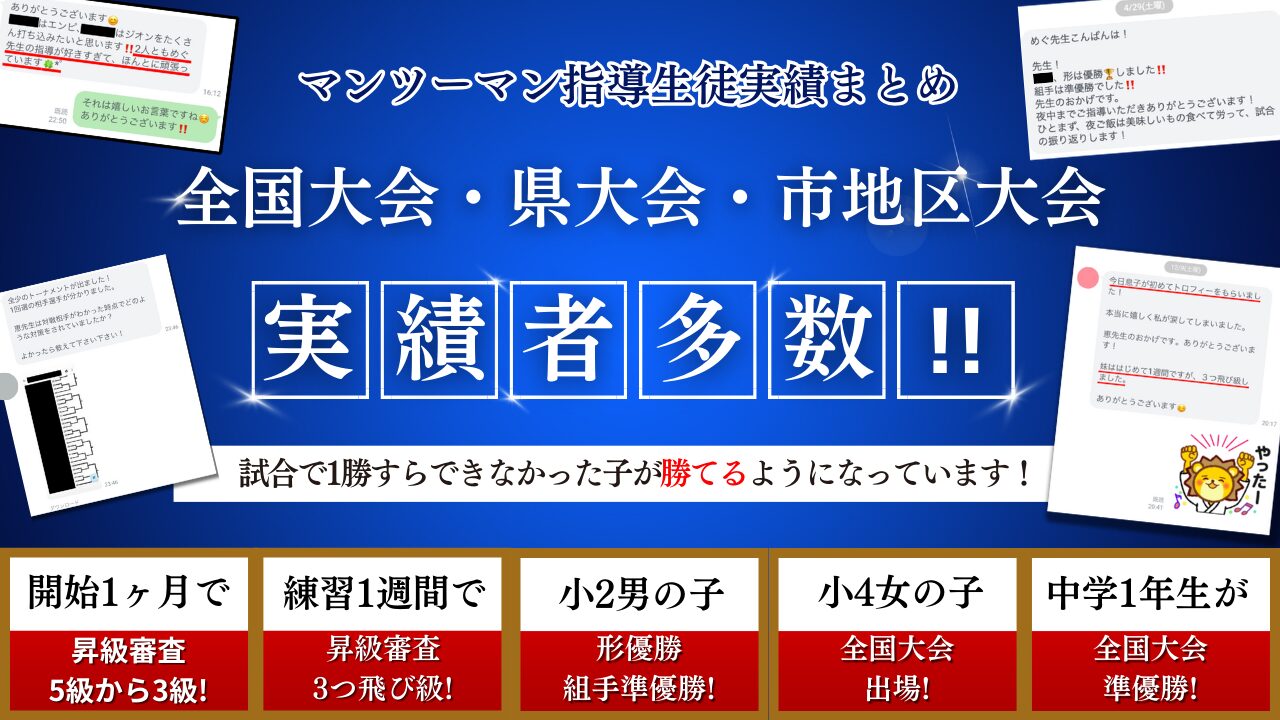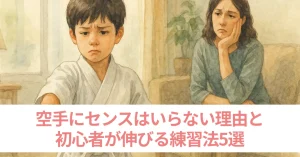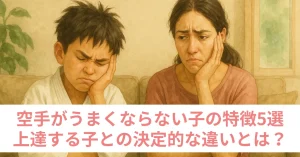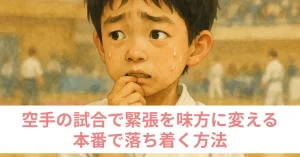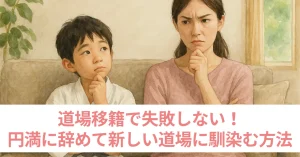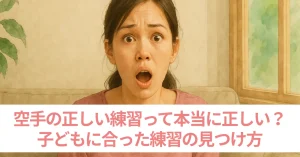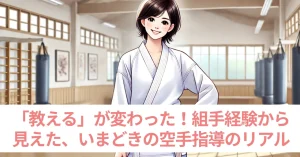「また今日も自主練しないで終わっちゃった…」
「自主的に練習できる子になってほしい」
「私が言わないと自主練しないんです…」
と、悩むことはありませんか?
空手に限らず、子どもが自主練を嫌がるのは多くのママが直面する悩みです。

無理にやらせても逆効果になることもあり、「どうしたらやる気になってくれるの?」と迷う気持ちもよく分かります。
この記事では、子どもが自然と体を動かしたくなる、自主練サポート法をご紹介します。
どれも今日からすぐに取り入れられる内容ばかりですので、ぜひ気軽な気持ちで読み進めてみてください。
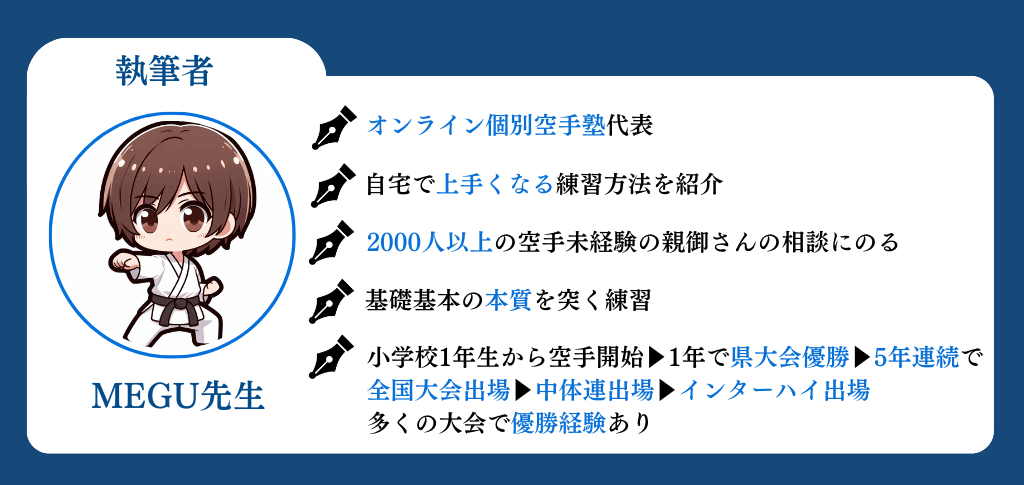
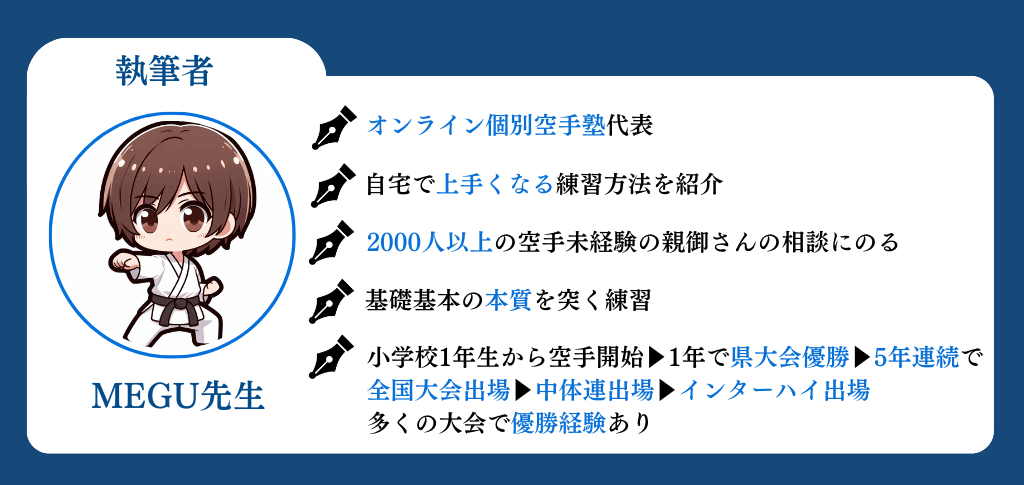
子どもが空手の自主練を嫌がる理由とは?
「試合で勝ちたい」「上手くなりたい」と言っている子どもたちがなぜ自ら進んで自主練をしないのでしょうか。
その理由は3つあります。
- 目的がわからない
- 自信がない
- やらされ感がある
お子さんに当てはまるものがないか確認してみましょう。
目的がわからない
子どもは「なぜ自主練をしなければならないのか」という目的を明確に理解していないことがあります。
ただ「やりなさい」と言われても、その意味が分からなければやる気は起きません。
空手の試合に勝つため、形(型)を覚えるためなど、目的を共有していないと、練習が単なる苦行になります。
大人でさえ、目的のない作業にモチベーションを保つのは難しいものです。
まずは「なぜこの練習が必要なのか」を子ども自身が納得できるようにしていくことが大切です。
自信がない
空手の技を覚えたり、うまくできるようになるには時間がかかります。
うまくできない自分に落ち込んでしまい、自主練に対してネガティブな印象を持つことも。
「どうせやってもできない」「また怒られるかも」と思うと、手が止まってしまいます。
そんな時こそ、小さな成功体験を重ねて「できるかも」と思える環境が必要です。
自信は練習の継続からしか生まれませんが、その第一歩は親の支えがカギになります。
やらされ感がある
子どもが自主練を嫌がる最大の理由は「やらされている」という感覚です。
「練習しなさい!」という言葉がプレッシャーになっていることも多いです。
やらなきゃ怒られる、という状況では、空手がどんどん嫌いになってしまいます。
本来は自分の成長のための練習なのに、親にやらされていると感じてしまうと、自主性は育ちません。
子どもが「自分でやる」と決められる空気を作ることが、自主練への第一歩です。
空手の自主練を習慣化する親の工夫
実際に自主練をしている子の親がどんな工夫をしているのか見てみましょう。
- 楽しい仕組みを作る
- 練習の意味を共有する
- 小さな達成を喜ぶ
楽しい仕組みを作る
子どもが続けやすいように、練習に「遊び」や「ゲーム性」を取り入れる工夫が効果的です。
例えば、タイマーを使って制限時間内に何回突きができるかを競ったりする方法があります。
また、スタンプカードやごほうびシールなどの「見える達成」もモチベーションにつながります。
練習=苦しいもの、というイメージを変えることが継続のカギです。
まずは「やってみたい」と思える工夫を親が一緒に考えてあげましょう。
練習の意味を共有する
自主練を継続するためには、「なぜこの練習をするのか」を子どもと一緒に考えることが大切です。
例えば「〇〇大会で優勝したいからから」など、いつまでにその目標を達成させたいのか。具体的な目標があれば練習に意味が生まれます。
ただ漠然とやらせるのではなく、目標に向かうステップとして自主練を位置づけましょう。
紙に書いて可視化することで、子ども自身も練習の意義を再確認できます。
練習を通じて目標に近づいている感覚を持てれば、やる気も自然とわいてきます。
小さな達成を喜ぶ
「うちの子褒めると調子乗るし、すぐサボるから…」と言って、成功体験をスルーしてしまう方もいますが、それはちょっともったいないです。
どんなに小さな進歩でも、「できたね!」と一緒に喜ぶことが子どもにとっては、大きな原動力になります。
「今日の突きは昨日より早かったね」など、変化に気づいてあげることがポイントです。
上達は目に見えにくいものですが、親がその変化を拾ってあげることで自信に変わります。
「ちゃんと見てくれてる」と感じることで、子どもはもっと頑張ろうと思えるのです。
継続の秘訣は、毎日の小さな「できた」を見逃さないことにあります。
子どものやる気を引き出す声かけ
これまで、自主練を嫌がる理由や習慣化についてお伝えしてきましたが、そもそも「やってみようかな」と思わせる工夫も必要です。
そこで、子どものやる気を引き出す声かけを3つ紹介します。
- 問いかけを使う
- 過程をほめる
- 共感を示す
お子さんの「やる気スイッチ」を探している方は、ぜひ参考にしてください。
問いかけを使う
普段あなたはお子さんにどんな声かけをしていますか。
例えば「早く自主練しなさい」「なんで練習しないのよ」みたいな感じで声かけをしていませんか?
もし自分がこんな言い方をされたら、「自主練しよう」と思えますか。おそらく反抗してしまいますよね…
だから、子どもに頑張ってほしいときこそ、命令口調よりも、問いかけの方が子どもの心に届きやすいです。
「今日、どの技やってみようか?」「形(型)の中でどこが難しかった?」など、考えるきっかけを与えることが大切です。
主体的に考えさせることで、「自分の練習」だという意識が育ちます。
問いかけは会話を増やす効果もあり、親子の信頼関係にもつながります。
子ども自身が答えを見つける手助けになるような声かけを意識しましょう。
過程をほめる
「結果が全てだ!」という方も中にはいらっしゃいますが、結果ではなく「頑張っていた過程」に注目してほめることが大切です。
「勝てたからえらい」ではなく「毎日コツコツやっててすごいね」と伝えましょう。
努力を認められることで、子どもは自分に誇りを持つことができます。
結果に一喜一憂しないことで、失敗を恐れず挑戦する姿勢も育ちます。
親が見てくれている、という安心感がやる気の土台になります。
共感を示す
「練習をやりたくないという気持ち」を否定せず、「そうだよね、疲れたよね」とまずは共感する姿勢が大切です。
子どもの気持ちに寄り添うことで、心の壁がほぐれていきます。
共感されたと感じると、子どもは気持ちを話しやすくなります。
感情に寄り添ってもらえた経験が、次への前向きな行動につながります。
中には、共感が難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、少しずつでいいのでお子さんの気持ちに共感してあげる。ぜひ、挑戦してみてください。
家庭でできる空手の自主練メニュー
実は、三日坊主で練習が続かなかった子どもたちでも、毎日自主的に練習するようになる練習メニューがあったんです。
ここでは、3つ紹介します。
- 基本動作を短時間で
- 親子でできる練習
- 遊び感覚のメニュー
すぐにできるものばかりですので、ぜひ試してみてください。
基本動作を短時間で
忙しい家庭でも取り組みやすいのは、基本動作を短時間で行うメニューです。
「短時間だけ練習させても意味がないよ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、全く自主練をしない子と少しでも毎日自主練をする子では、1年後にどれだけの差が出るのかを少し見てみましょう。
例えば、突きの練習を毎日60回する子と、全く自主練しない子がいたとします。
毎日60回突きの練習をすると、1ヶ月で約1,800回。
3ヶ月で、約5,400回。6ヶ月で、約10,800回。1年間で、約21,600回。
1年後には、自主練をする子としない子で、突きの回数に約21,600回もの差が生まれるんです。
ちょっとした差でも、長い目で見るとこんなに大きな結果になるんです。
だから、忙しい子でも毎日10分だけでもいいので、突きや蹴り、構えの練習に集中する。これだけで、十分な効果を実感できますよ。
もし子どもの集中力が続かない場合は、時間を決めて「タイマー練習」にすると取り組みやすくなります。
短くても継続することで、自然と体に技がしみこんでいきます。
親子でできる練習
親が一緒にやることで、子どもは楽しく取り組みやすくなります。
例えば、子どもがやっている突きや蹴りの練習を真似してみる。
実践形式で組手の練習をしながら、親御さんがお子さんの突きを受けたり、払ったりするだけでも十分な練習になります。
また「競争しよう!」と声をかければ、子どもは楽しみながら集中しやすくなります。
親が楽しんでいる姿を見せることが、子どもにとっては励みになります。
一緒に過ごす時間が、親子のコミュニケーションを育む大切な時間にもなるでしょう。
遊び感覚のメニュー
子どもが飽きずに繰り返せるように、ゲーム感覚での練習もおすすめです。
例えば「連続で〇回できたらクリア」「パパと対決して勝てたらポイント」など、ルールを決めて取り組むと楽しくなります。
ただの反復練習も、目標があるだけで意欲が大きく変わってきます。
兄弟や家族も巻き込めば、家庭全体で取り組める空気が生まれます。
ゲーム性を加えることで、自主練が「日課」から「楽しみ」に変わります。
空手を通じて自主性を育てるコツ
空手を通じてお子さんの自主性を育てるコツを5つ紹介します。
- 子どもの想いを尊重
- 長期的に見守る
- 失敗を恐れず挑戦させる
- 子ども自身に練習内容を決めさせる
- 1つのやり方にこだわりすぎない
それぞれ見ていきましょう。
子どもの想いを尊重
親の期待ではなく、子どもがどうしたいのかを尊重することが大切です。
「勝ってほしい」「上手になってほしい」という気持ちが強すぎると、子どもは重荷を感じます。
「自分がどうなりたいか」を子ども自身に考えさせるようにしましょう。
その中で出てきた想いを応援していくスタンスが、長く続ける力になります。
「あなたの空手」だという意識が、自主性を支えていきます。
長期的に見守る
空手の上達も、自主性の成長も一朝一夕にはいきません。
「今すぐできるようにする」ではなく「時間をかけて育てる」意識が必要です。
失敗やスランプも、成長の過程として見守りましょう。
長い目で見て応援し続けることが、子どもの力を引き出します。
継続の鍵は、焦らずに信じて見守ることにあります。
失敗を恐れず挑戦させる
「子どもに失敗させたくない」と感じていると、大人がどうしても先に手を出したくなってしまいます。
しかし、それが続くと、子どもは自分で解決策を見つける力を養えなくなってしまう恐れがあります。
失敗を恐れず、挑戦できる場を提供することが重要です。失敗も成長の過程として、貴重な経験となることがあります。
失敗を過度に避けるのではなく、挑戦させることが、最終的に子どもの自主性を育てることに繋がります。
子ども自身に練習内容を決めさせる
毎回、親が練習メニューを決めるのではなく、その日練習したい技を自由に選ばせるのも良い方法です。
例えば、「今日は好きな技を3つ選んで、10分ずつ練習してみよう!」と声をかけ、子どもが自分のペースで練習内容を決めることを促します。
これにより、練習に対するモチベーションも上がり、自分で考えて練習メニューを作れるようになります。
1つのやり方にこだわりすぎない
空手に限らず、1つのやり方にこだわりすぎないことはとても大切です。
例えば、練習メニューに変化を加えることで、子どもの興味を引き続き保ち、やる気を引き出すことができます。
場合によっては、異なる方法を試してみたり、時には他の道場での練習を体験させたり、オンラインの空手サロンに参加し、新しい刺激を与えることも有効です。
また、空手の上達には多様なアプローチがあり、形(型)や組手、体力作りに至るまで、さまざまな練習法が効果を発揮します。
固定観念に囚われず、子どもの特性や気分に合わせた方法を試すことで、より効果的に技術を向上させることができるでしょう。
最も大切なのは、柔軟に考え、子どものペースに合わせ子どもがどうしたいのかを考えさせることが大事です。
まとめ:「やらせる練習」ではなく「やりたくなる練習」に
子どもが空手の自主練を嫌がるのは、決して珍しいことではありません。
だからこそ、ママが「どう接するか」「どう環境を整えるか」がとても大切です。
今回ご紹介した方法は、いずれも「やらせる」のではなく、「やりたくなる」仕組みづくりがポイントです。
練習時間を短くして気軽に取り組めるようにしたり、ママ自身が楽しむ姿を見せることで、子どもの心が動きやすくなります。
「やらないとダメ!」という気持ちを一度手放し、子どもと一緒に楽しむ姿勢で取り組んでみてください。
きっと、少しずつ変化が見えてくるはずです。